Contents
◎Live Review
Father John Misty at TSUTAYA O-EAST
◎Recommended Albums
Wes Montgomery『In Paris: The Definitive ORTF Recording』, Kevin Hays / Lionel Loueke『Hope』, Jack DeJohnette『Hudson』, GoGo Penguin『A Humdrum Star』, Tore Brunborg / Steinar Raknes『Backcountry』, V.A.『Innerpeace』, Van Morrison『You're Driving Me Crazy』
◎Coming Soon
Nick Lowe
◎PB’s Sound Impression
Jazz Spot「Nefertiti」
構成◎山本 昇
Introduction
今回のA Taste of Musicは、千葉県柏市にあるジャズ・スポット「ネフェルティティ」にやって来ました。柏のジャズ・スポットと言えば今年の2月、「ナーディス」というお店に女性ヴォーカルとダブル・ベイスのデュオで、2016年の「LIVE MAGIC!」にも出てもらったアルヴァスを観に来たばかりです。もっともそのときの公演は、女性ヴォーカリストのサラ・マリエル・ガウプが、間違えて娘のパスポートを持ってきてしまって出国が遅れたためスタイナー・ラクネスの単独コンサートとなってしまったのですが、僕は元々、彼のソロが大好きだったので、全く損した気にはなりませんでした。次のソロ・アルバムに収録する予定の曲も披露してくれたので、むしろ得した気分を味わいました。ここ「ネフェルティティ」でも、コンサートやイヴェントがたくさん行われているそうですね。
というわけで今回は、ジャズ・スポットにちなみ、僕がいまお勧めしたいジャズ作品を中心にお届けしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

アルヴァスのサラ・マリエル・ガウプ(左)とスタイナー・ラクネス

Live Review
独特の感性で観客を引き込んだ
ファーザー・ジョン・ミスティのステージ

シンガー・ソングライターのファーザー・ジョン・ミスティ。2018年2月15日、TSUTAYA O-EASTのステージから [photo by Kazumichi Kokei]
2月にTSUTAYA O-EASTで行われたファーザー・ジョン・ミスティの来日公演を、僕はアルバム1枚だけ聴いて観に行こうと思いました。元々はJ・ティルマンという名前でやっていたアメリカのシンガー・ソングライターですが、2012年頃からファーザー・ジョン・ミスティを名乗っています。来日メンバーはけっこう人数が多くて、歌いながらギターも弾くファーザー・ジョン・ミスティの他にギタリストが二人、キーボードも二人いて、あとはベイスとドラムズ。二人のギタリストとベイシストのところにもキーボードがあって、曲によっては全員がキーボードを弾いてみたり(笑)、あまり観たことのない展開もありました。
全体的に派手さはないけれど、音楽における強弱の使い分けがすごく印象的でした。ステージングそのものはシンプルで、照明などで驚かすようなことはありません。ファーザー・ジョン・ミスティ本人はお客さんにアピールするにあたり、格好つけているというわけでもないんだけど、どこか自分の格好良さは意識しているというか……。でも、それが全然嫌味じゃないんです。
僕はファーザー・ジョン・ミスティ名義の最新作の『Pure Comedy』くらいしかよく聴いていなかったから、セット・リストの半分は知らない曲でしたが、全く飽きることはなく、すごく引き込まれました。この人が書く歌は歌詞がなかなか面白くて、世相を斬ったものなどかなり皮肉の込められた曲が多いんです。非常にドライなのですが、そのあたりの感覚もまた格好いい。社会や政治を皮肉ったかと思うと、自分のことも皮肉っていたりするから嫌味がないんですね。自嘲的な歌詞の曲もけっこうありますが、ヴォーカリストとしても味があって、ただ歌詞が面白いというだけじゃない。とても才能あるシンガー・ソングライターですから、次に来日するときもまた観てみたいですね。
◎Information
ファーザー・ジョン・ミスティの最新作『GOD'S FAVORITE CUSTOMER』が6月1日にリリース決定!

ファーザー・ジョン・ミスティ『Pure Comedy』ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ OTCD-6098

ファーザー・ジョン・ミスティ『GOD'S FAVORITE CUSTOMER』ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ OTCD-6435(6/1世界同時発売)

[photo by Kazumichi Kokei]

[photo by Kazumichi Kokei]

[photo by Kazumichi Kokei]

[photo by Kazumichi Kokei]

[photo by Kazumichi Kokei]

[photo by Kazumichi Kokei]
Recommended Albums
いまお勧めしたい
7枚のジャズ関連アルバム

今回は千葉県柏市にある「ネフェルティティ」のオーディオでジャズ作品を中心に試聴
唯一のヨーロッパ・ツアーを収めた音源が発掘される
Wes Montgomery『In Paris: The Definitive ORTF Recording』
1965年3月、パリのシャンゼリゼ劇場で行われたコンサートのライヴ録音です。元々はフランスの国営放送で録音されたものですが、最近になってこの放送局のアーカイヴが整理され、少しずつレコード化されるという動きが始まっていて、このアルバムを発掘したのはアメリカのResonance Recordsというレーベルです。ウェス・モンゴメリーは、どうやら飛行機が大の苦手だったらしく、海外ツアーはこのときの1回だけしかやっていないそうですね。当時はイギリスのテレビにも出ていたんじゃないかな。
Black Lion Recordsというイギリスのジャズ・レーベルのプロデューサーだったアラン・ベイツは、ウェスを欧州でのツアーに誘い出すため、「とにかくヨーロッパまで来てくれれば、あとは全部電車で回るから」と言って説得したと、ライナーノーツに書いてあります。そうやってなんとか飛行機に乗せてやってこさせたというわけですね。僕は個人的にもウェス・モンゴメリーは好きですが、アルバムをそんなにたくさん持っているわけではありません。初めて聴いたウェスのレコードは、クリード・テイラーがプロデュースしたCTIの作品でした。オーケストラなどを多用した編曲は当時の僕にはトゥー・マッチで、拒否反応があったんです。後に、カリフォルニアのライヴを収めた『Full House』やジミー・スミスと共演した『Dynamic Duo』など、もっと前のアルバムを聴いていいなと思いました。1960年に発売された『Movin’ Along』や、代表曲の一つ「Four On Six」が入っている『The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery』もよく聴いていました。また、1965年にウィントン・ケリー・トリオと行ったセッションを収録した『Smokin' At The Half Note』も好きですね。
WOWOWの番組『オフビート&JAZZ』でもウェスのライヴを取り上げたことがありました。ご存知の方もいると思いますが、彼はギターを弾くときにピックを使いません。ほとんど親指1本で演奏する姿には、観ていて度肝を抜かれる思いがしました。コード弾きもソロも、親指だけというのはちょっと信じられないところですが、そんなエピソードもさることながら、彼の演奏は本当に素晴らしいです。
『In Paris』は、そんなウェス・モンゴメリーの小編成コンボ・スタイルによるライヴで、演奏は抜群だし、音もすごくクリアに録れています。オリジナル・テープをアメリカでリミックスしたらしいのですが、とてもきれいな音に仕上がっています。
ジャズにおけるギタリストの役割もいまや大きくなりましたが、ウェス・モンゴメリーはその意味でも草分け的な存在と言えるでしょう。ウェスの前にはチャーリー・クリスチャンがいて、ジャズ・シーンにおけるソロ・ギタリストとして脚光を浴びるようになります。それまではジャズと言えばリズム・ギターが中心で、カウント・ベイシーのところのフレディ・グリーンらが有名だったし、確かビリー・ホリデイのお父さんもジャズ・ギタリストだったと思います。でも、その頃はまだソロ・ギターを弾く人はほとんどいなかったはずだから、チャーリー・クリスチャンの存在は衝撃的だったわけですが、彼は25歳という若さで亡くなってしまいます。ベニー・グッドマンのバンドで活動していたのもほんの数年でしたが、戦時中にモダーン・ジャズが生まれようとしている時期、セロニアス・マンクたちがハーレムの小さなクラブ「ミントンズ・プレイハウス」で夜な夜な行っていた新しい試みに、チャーリー・クリスチャンも参加していました。ただ、その頃には持病の結核が悪化していたようですね。
その後はというと、バーニー・ケセルやジム・ホールなど何人かが思い浮かびますが、当時のジャズ・ギタリストの多くはボディに厚みのあるセミ・アクースティックで、柔らかいサウンドを奏でていました。いま聴くといいんですが、若い頃の僕にはいまひとつインパクトに欠けるというか(笑)、気に留めることはほとんどありませんでした。
ウェス・モンゴメリーもそんなに刺激的な音を出す人ではないから、僕も10代に聴いていたなら、そんなに引っかかることはなかったかもしれません。70年代以降はジャズ・ギターの世界にも、ラリー・カールトンといったロックの影響も受けたフュージョン世代の人たちが次々と登場しました。そして、ジョン・スコフィールドやビル・フリゼルは僕と同じ1951年生まれで、ビートルズやストーンズ、ジミ・ヘンドリクスを聴いて育っています。もちろん、昔のジャズ・ギターのことも研究しているはずですが、ギターのトーンは60年代以降の音色を使っていますよね。この世代がバリバリ活動するようになってから、ジャズの中でもギターの存在感は増していったと思います。まぁ、大きく変わっていったのは70年代のフュージョンからでしょう。パイオニア的な存在と言えば、ジョン・マクラフリンや昨年亡くなったラリー・コリエルといった個性派もいました。そんな彼らもきっと、ウェスのことは尊敬していたことでしょう。60年代から活躍した大好きなギタリストにグラント・グリーンがいますが、Resonance Recordsから彼のフランスとカナダの未発表ライヴ盤が5月に出るので楽しみです。ちなみに、A Taste of Music Vol.22で取り上げたジャコ・パストリアスの『Truth, Liberty & Soul』が出たのもResonance Recordsからでした。

ウェス・モンゴメリー『In Paris: The Definitive ORTF Recording』キングインターナショナル KKJ-1025(国内仕様CD/2枚組)
要注目のピアニストと
ギタリストによるデュオ
Kevin Hays / Lionel Loueke『Hope』
先ほどお話ししたResonance Recordsのこの一連の作品を企画しているゼヴ・フェルドマンというアメリカ人のプロデューサーにたまたま会いました。場所は東京で行われたあるライヴ会場だったのですが、それがケヴィン・ヘイズというミュージシャンの来日公演だったんです。僕はこのピアニストのことをそれまで全く知りませんでした。ラジオ番組のリスナーから、地元のライヴハウスでこの人のコンサートを観たらすごく良かったということでリクエストが来たんです。そこでいろいろ調べて聴いてみたら、なかなかいいんですね。
その彼の最新作が、ギタリストのリオネル・ルエケと共演した『Hope』というアルバムです。Newvelle Recordsというフランスの小さなレーベルからの発売で、「ラジオでかけたいから、圧縮音源でいいのでデータを送ってくれませんか」とメールを出したら、驚いたことに「うちはアナログ・レコードしか出していません」と。「データで送れないこともないけれど、できればアナログで聴いてほしい。すぐに送りますから」って(笑)。物が届いてビックリしたのは、『Hope』がセカンド・シーズンとなるボックスの中の1枚だったことです。アナログ・レコードの6枚組で、それがサブスクリプションのようになっているんですね。
このアルバムのA面の最後「Feuilles-O」はハイチのトラディショナル・ソングをケヴィンが編曲し、ルエケが歌っています。ベイシストで歌手のリチャード・ボナにちょっと近いような歌で、これもすごく気持ちがいい。ニューヨークのイーストサイド・サウンドというスタジオで、2016年の9月6日と7日の2日間で録音しています。リハーサルも軽く行ったでしょうけれど、わりとその場での展開だったんじゃないかと想像します。ずこく息の合った演奏ですね。
ルエケは西アフリカのベナン出身で、いまはアメリカで活動しています。ハービー・ハンコックに起用されることも多くて、ハービーと一緒に日本に来たこともあるし、自身のトリオで来日した一昨年のコットンクラブでの公演はA Taste of Music Vol.12の“Coming Soon”でもご紹介しました。そのときの印象は、ソロ楽器はギターだけだったけど、リードとリズム両方の要素がすごく強くて、ときにセロニアス・マンクをギターに置き換えたような不思議な感覚もあったり、とても刺激的なギターだなというものでした。その後にもう一度、ピットインでも観たんですが、そのときはあまりにも先走り過ぎて、ちょっと難しくてついていけなかったんです。この人の頭の中は相当すごいことになっていると思います。つまり、そう簡単に付き合えるギタリストではないわけですが(笑)、このアルバムはとてもいい感じでした。ルエケは昨年の11月に、ドイツ出身の女性ヴォーカリスト、セリーヌ・ルドルフとのデュオで『Obsession』というアルバムを出しましたが、これもなかなか良かったです。
ケヴィン・ヘイズというピアニストは今年で50歳、90年代の初めから活動していてアルバムもたくさん出しています。ブルーノートからも3枚ほど出しているし、ブラッド・メルダウと一緒に作ったレコードもありますね。この2月に新宿ピットインで観た、ハーモニカ奏者のグレゴア・マレとの来日公演もとても良かった。注目したいミュージシャンが、また一人増えたという感じですね。

ケヴィン・ヘイズ/リオネル・ルエケ『Hope』
ジャズ界のベテランが
ウッドストック縁の曲をカヴァー
Jack DeJohnette『Hudson』
現在75歳のジャズ・ドラマー、ジャック・ディジョネットの最新録音が『Hudson』です。メンバーはジャックのほか、ギターにジョン・スコフィールド、キーボードにジョン・メデスキ、ベイスにいちばん若いラリー・グレナディアが参加しています。“Hudson”は、彼らのプロジェクト名でもあるようですが、ニューヨーク州の北部にあるハドソン川上流の谷“ハドソン・ヴァリー”のことで、メンバーが全員そこに住んでいるらしいんです。そして、あのウッドストックも同じ地方になります。
このアルバムは、全11曲のうち、ジャックの曲が3曲とスコフィールドの曲が2曲、全員で作った1曲を除いた5曲はすべてウッドストックに縁(ゆかり)のある人たちの曲のカヴァーで、ボブ・ディランの「Lay Lady Lay」と「A Hard Rain's A-Gonna Fall」、ザ・バンドの「Up On Cripple Creek」、ジミ・ヘンドリクスの「Wait Until Tomorrow」、ジョーニ・ミッチェルの「Woodstock 」を収録しています。また、日本盤にはもう1曲、ジミ・ヘンドリクス「Castles Made of Sand」のカヴァーも追加収録されています。ちなみに、ジョーニ・ミッチェルはウッドストック・フェスティヴァルには出演していません。ニューヨークのデイヴィッド・ゲフィンのアパートで、その様子をテレビで見ながらこの曲を書いたそうです。
ではその中から、8曲目の「Dirty Ground」を聴いてみましょう。これはジャックがブルース・ホンズビーと共作した曲で、以前発売されたジャックのソロ・アルバムでも録音していました。そのときにはブルース・ホンズビーが歌っていましたが、ここでは珍しくジャック自身がヴォーカルをとっています。ニュー・オーリンズのマルディ・グラ・インディアンのことを歌った曲です。
このアルバムを、ジャズ作品と言っていいかはともかく、メンバーは全員ジャズの世界で活動している人たちです。ただ、先ほども少しお話ししたように、ジョン・スコフィールドはロックも聴きながら育った世代だから、そういう部分が垣間見られることもある。このアルバムは、僕にとってはまさにドンピシャで、2017年の年間ベスト10の一つにも選んだほど、よく聴きました。演奏は素晴らしく、この面子ならではのものと言えます。ジョン・スコフィールドとジョン・メデスキは、メデスキの“メデスキ、マーティン&ウッド”というトリオにスコフィールドが加わる形でときどき一緒にやっていて、アルバムも3枚ほど出ていますね。“Hudson”としては、アメリカでライヴもやっているようですが、日本でもぜひ観てみたいですね。「Live Magic!」に呼びたいところだけど、ちょっと高すぎて無理かなぁ(笑)。
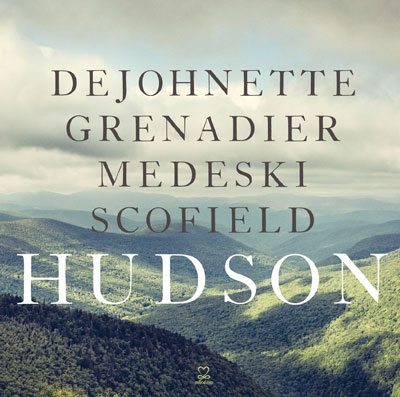
ジャック・ディジョネット『Hudson』ソニーミュージック SICX-90
![ジャック・ディジョネット、ジョン・メデスキ、ラリー・グレナディア、ジョン・スコフィールド(左から)[photo by Nick Suttle] image v25_15](https://www.a-taste-of-music.jp/wp/wp-content/themes/atom_1.0/images/vol25/v25_15.jpg)
ジャック・ディジョネット、ジョン・メデスキ、ラリー・グレナディア、ジョン・スコフィールド(左から)[photo by Nick Suttle]
更新された耳に馴染む
新感覚トリオの最新作
GoGo Penguin『A Humdrum Star』
若手ピアノ・トリオ、ゴーゴー・ペンギンが今年2月に出した最新作が『A Humdrum Star』です。イギリスのマンチェスターを拠点に活動していて、テクノやダンス・ミュージックなどからも影響を受けているようです。実際に、ドラムズにしても例えばエレクトロニカのようなビートを生で叩いていたりします。そうしたバンドは多いですが、ゴーゴー・ペンギンはそんな中でも独自の感性を持っていると思います。音はどちらかというとイギリス寄りで、どこかどんよりとした雰囲気もありますが(笑)、決して嫌な感じはしません。
最近、ジャズと呼ばれるものにこうしたタイプの音楽が多くなっています。リズム的にはやはりピップ・ホップの影響がすごく強いわけですけれど、なんかもうそれが普通になってきましたね。ロバート・グラスパーがブルーノートでアルバムを出し始めてからすでに10年以上が経っています。こうした時間の流れというのは意外に大きくて、僕も10年前はまだエレクトロニカに違和感があったと思うけれど、基本的にアクースティック楽器での演奏の中にそれらの要素を採り入れる彼らの音楽はすんなりと耳に入ってきました。2月のブルーノート東京でのライヴも楽しみにしていたんですが、僕が当日に熱を出してしまって残念ながら観られなかったので、次の機会にはぜひ観たいと思っています。
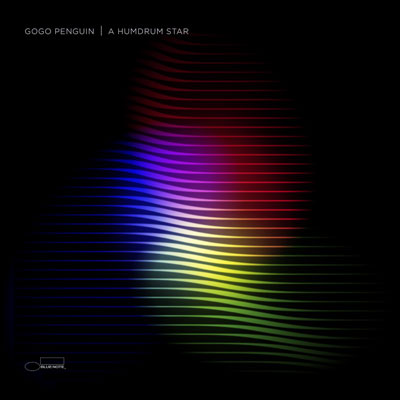
ゴーゴー・ペンギン『A Humdrum Star』ユニバーサルミュージック UCCQ-1080
ダブル・ベイスとテナーによる異色のデュオ
Tore Brunborg / Steinar Raknes『Backcountry』
冒頭でお話ししたノルウェーのベイシスト、スタイナー・ラクネスが、「ナーディス」でのコンサートの別れ際に1枚のCDをくれました。やはりノルウェーのサックス奏者であるトゥーレ・ブルンボルグと作った『Backcountry』というアルバムなのですが、聴いてみるとこれもいい作品でした。1曲目の「Blooming」を聴いてみます。ダブル・ベイスとテナー・サックスという異色のアクースティック・デュオですが、僕はこういう小編成での音楽の掛け合いが好きな人間の一人です。どちらも基本的には単音の楽器なのに、聴くとよく分かりますが、足りないものは何もなく、これで十分に成り立ちます。
ECM作品でよく知られるオスロのレインボー・スタジオで、1日で録り上げているようです。このスタジオお馴染みのエンジニア、ヤン・エリック・コングスハウクがレコーディングとミックス、マスタリングを手掛けています。あのスタジオとこのエンジニアの音はやはりいいですね。
スタイナー・ラクネスはジャズ畑のミュージシャンですが、いろんな音楽をやる人で、冒頭にお話ししたアルヴァスは北極圏のサーミという少数民族の女性ヴォーカリストとのユニットです。また、彼のソロ・アルバムでは、アメリカーナの曲を英語で歌ったり、ほかのメンバーの音がちょこっと入ったりするけど、ほとんどダブル・ベイスが中心となっている作品もあるなど、とにかく面白いことをやる人です。
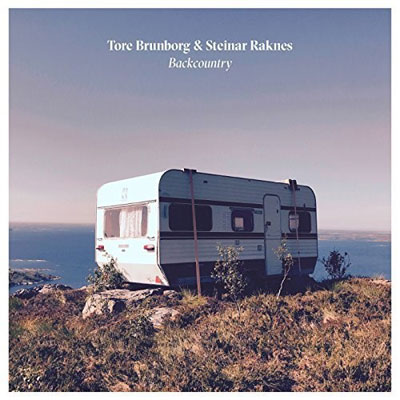
トゥーレ・ブルンボルグ/スタイナー・ラクネス『Backcountry』
Mainstream Recordsの埋もれたレア音源を復刻
V.A.『Innerpeace』
ボブ・シャドというプロデューサーが70年代にやっていた、恐らく当時はほとんど売れていなかったであろうMainstream Recordsというレーベルの音源を、フランスのWewantsounds(ウィ・ウォント・サウンズ)という小さなレーベルが『Innerpeace』という2枚組のコンピレイションにして出しています。彼らの言うスピリチュアル・ファンク−−−まぁ、いわゆるレア・グルーヴ的なものですが、こういう形で復刻される音源も最近けっこう増えてきましたね。ちなみに、Wewantsoundsの主宰者はフランス人ですが、佐藤博の『Orient』という1979年のアルバムも再発していて、ヨーロッパでは最近70年代から80年代の日本の音楽が遅まきながら注目されていると言います。
1枚目のB面の頭からサックス奏者、バディ・テリーの1973年の曲「Innerpeace」を聴いてみましょう。この曲のドラムズはバーナード・パーディ。おかずも「出ました」って感じですね(笑)。ベイスはウィルバー・バスコム、ギターはジェイ・バーリナーですから、割と有名なスタジオ・ミュージシャンが集められています。その次の曲はやはりサックス・プレイヤーのハドリー・カリマンによる「Cigar Eddie」ですが、こちらはドラムズのクラレンス・ベクトンの名前に見覚えがあるくらいで、特に有名な人はいませんが、なかなかいい曲なんですよ。1971年の曲ですが、当時はジャズとファンクが一緒になったような、モーダルというか何というか、そんなタイプのレコードが無数に出ていたんですね。僕もこのMainstream Recordsというレーベルは覚えていますが、割とB級っぽいイメージがありました。いまの若い人にとっては、こうしたほとんど誰も聴いたこともないようなアナログの音源を掘って、その中からいい曲を見つけるのが使命だと感じられるのかもしれませんね。
僕も1990頃、初めてCDのコンピレイションを作らないかと誘われて、ブルーノート・レーベルの音源の中からあまり知られていないハモンド・オルガンの音源を選んだ『Soul Fingers』を監修したときは、いい曲をみんなに紹介できるのが嬉しかったんですよ。だから、このレコードを通じて、作った人たちの楽しさも分かる気がします。いわゆるジャズの歴史に残るような名演ではないけれど、例えばクラブでこういう曲がかかればすごく気持ちがいい。Wewantsoundsのサイトを見たらアナログ・レコードは完売したようですが、CDも出ています。
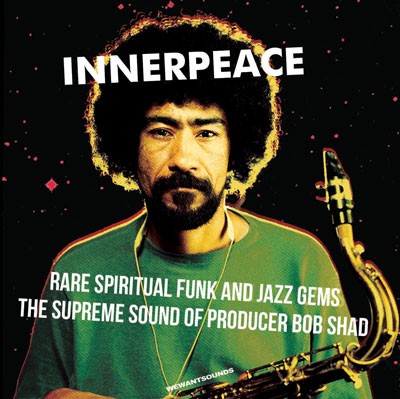
V.A.『Innerpeace』
ジャズ・オルガニストとの共演で贈る39作目の新録音
Van Morrison『You're Driving Me Crazy』
ヴァン・モリソンが、ハモンド・オルガン奏者のジョーイ・デフランチェスコと組んでニュー・アルバム『You're Driving Me Crazy』(5月2日発売)を作りました。アルバム・タイトル曲の「You're Driving Me Crazy」では、わりと普通にジャズらしく歌っているヴァンですが、コール・ポーターの有名曲「Miss Otis Regrets」は、言われなければ分からないくらいに(笑)、完全にメロディを崩しています。この人は最近、とにかく次々とアルバムを出していて、昨年12月に『Versatile』を作ったばかりですが、この『You're Driving Me Crazy』はそれに次ぐ39枚目のスタジオ作品です。ジャズやブルーズの有名曲のカヴァーと、ヴァン自身の昔の曲や最近になって作った曲を半々くらいの割合で、ジョーイのグループをバックに歌っています。カヴァー曲も、ヴァンにとってはお手の物だったと思うから、録音もすんなり行われたんじゃないかと思います。彼は歌をテイク1か2でキメるのが好きなようですからね。
現在46歳のジョーイ・デフランチェスコがデビューしたのは16歳でした。ちょっとC調なところがあるけれど、オルガン奏者としてのテクニックはすごい。ただ、そのものすごい早弾きには、「はい分かりました。それで?」というところもありました。トランペッターでもある人で、このアルバムのトランペットもジョーイが吹いているはずです。
今年で73歳になるヴァン・モリソンですから、もうちょっとゆっくりやってもいいはずなんだけど(笑)、ものすごいペースでアルバムを出しているからビックリさせられます。ヴァン・モリソンには職人的なところがあって、「オレが音楽をやっているのはメシを食うためだ」と、はっきり公言しています。そんな割り切りがあるからこそ、こんなにたくさんアルバムが出せるのかもしれませんが(笑)。ただ、ついこの前離婚したというニュースも発表されましたから、もしかしたら慰謝料を稼がなくちゃならないのかな?
僕は初期の『Moondance』(1970年)や『It’s Too Late to Stop Now』という1974年のライヴ盤あたりが大好きですが、最近では2015年に出た『Duets: Re-working the Catalogue』というアルバムで、自身の過去の作品の中からこれまであまり注目されなかった曲をあえて取り上げて、好きなヴォーカリストとデュエットしているのですが、これはすごく良かったんです。久々のヒットだなと思ったヴァン・モリソンのレコードでした。その後にもちょこちょことアルバムが出てきて、どれもそれなりにいいんですけれど、ここまでたくさんだと、軽く見られてしまうのではないかと、変な心配をしてしまいます(笑)。今回は、ちょうどジャズもフィーチャーされたアルバムだったので、紹介させてもらいました。
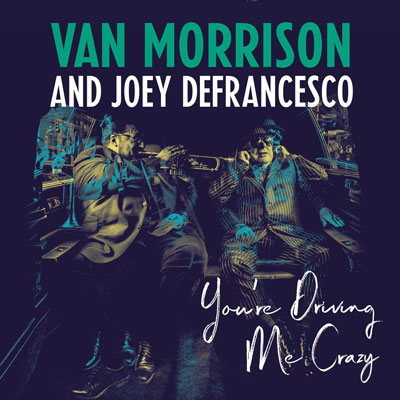
ヴァン・モリソン『You're Driving Me Crazy』ソニーミュージック SICP-5759(5/2発売)
Coming Soon
名プロデューサーとしても知られる
シンガー・ソングライターの日本公演
NICK LOWE
Billboard Live TOKYO
2018 4.30 mon 1st Stage Open 15:30 Start 16:30 / 2nd Stage Open 18:30 Start 19:30
2018 5.1 tue 1st Stage Open 17:30 Start 19:00 / 2nd Stage Open 20:45 Start 21:30
Billboard Live OSAKA
2018 5.4 fri 1st Stage Open 15:30 Start 16:30 / 2nd Stage Open 18:30 Start 19:30

昨年も来日したニック・ロウが今年もやって来ます(ビルボードライブ東京[2018年4月30日(月)~5月1日(火)/ビルボードライブ大阪[2018年5月4日(金)])。1949年生まれの彼は、70歳を目の前にして、すでに髪の毛は真っ白ですが、いまでもフサフサとしていて、声もほとんど衰えていません。日本ではニュー・ウェーヴ時代のエルヴィス・コステロのプロデューサーをやっていた時代のイメージが強いと思いますが、歳を取るにつれて渋いミュージシャンに発展して、元々の彼が影響を受けていたアメリカ南部のカントリーやリズム&ブルーズが合わさったような、すごくいい曲を作るシンガー・ソングライターになっています。最近も、アルバムの数こそ多くはありませんが、十分にいい作品を残しています。ソロでもバンドでも、いつも聴き応えのある人です。
今回も去年と同じく単独での来日公演ですが、ギター1本でも充実したステージになるでしょう。観に来る人たちも曲をよく知っているから、会場全体での合唱も始まるのではないかと想像します。以前はバンド形式で来たこともありましたが、長年の付き合いだったドラマーのロバート・トレハーンが3年ほど前に亡くなり、彼に代わるドラマーがいないのか、いまはライヴについてはソロのほうがいろんな意味で気軽にできるのかもしれません。
ニック・ロウは2000年以降も、いちばん新しいクリスマス・アルバム『Quality Street: A Seasonal Selection for All the Family』(2013年)を含めて4枚のソロ・アルバムを発表しています。2001年の『The Convincer』もいいアルバムでしたが、その次の『At My Age』(2007年)が素晴らしかったですね。2011年の『The Old Magic』にも好きな曲がありました。そして今度、アルバムではありませんが、45回転のシングル盤2枚組(合計4曲)の形で久しぶりの新曲を発表します。そのタイトル曲は何と「Tokyo Bay」です。
イギリス人らしい自嘲的なところはあるけど、性格はいい人です。地味だけどクオリティの高い音楽を作り続けています。ライヴも何度見ても飽きない人ですから、今年も僕は足を運びたいと思っています。
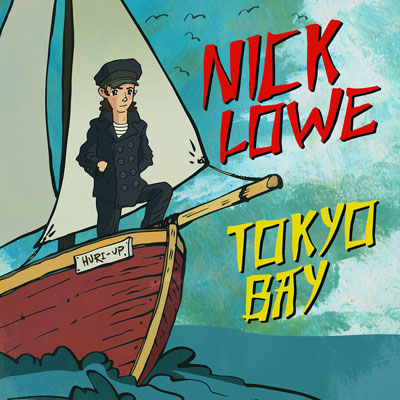
ニック・ロウ『Tokyo Bay』(EP)













































































