◎Featured Artists
ROBERT GLASPER and OMAR SOSA
◎Recommended Albums
ROBERT GLASPER『Double Booked』
OMAR SOSA & THE AFRI-LECTRIC EXPERIENCE『Eggūn』
◎Coming Soon
CÉCILE McLORIN SALVANT
構成◎山本 昇
A Taste of Music第2回目の今回は、新しいジャズを巡る興味深い2つのライヴについてお話ししたいと思います。僕は9月の中旬にブルーノート東京で行われたロバート・グラスパーとオマール・ソーサのステージを立て続けに観ました。ヒップホップへの接近を試みるグラスパー、そしてワールド・ミュージックとしてのアプローチをジャズに採り入れているソーサ。どちらも大変魅力的なミュージシャンです。この2人にスポットを当てる前にまず、ジャズが他の音楽要素をいかに取り込んでいったかを考えてみたいと思います。
誰もが「これがジャズだ」と呼べるジャズはいつ頃まであったのでしょう。僕が思うに、それは60年代後半くらいまでではなかったでしょうか。例えばマイルズ・デイヴィスがエレクトリックに転じ、ファンク・サウンドを採り入れるようになった頃、彼はすでに自らの音楽をジャズとは言わなくなりました。アルバム『イン・ア・サイレント・ウェイ』のクレジットには“Directions in Music By Miles Davis”と記されています。やがて70年代に入り、ジャズは常に新しい形を求めて、周辺のいろいろな音楽の要素を採り入れつつ、変わっていきました。ウェザー・リポートやハービー・ハンコック、チック・コリア、あるいはクルセイダーズもそうですね。最初は暗中模索だったのでしょうけれど、商業的に成功するようになると、フュージョンと呼ばれるものが出てきたりして、やや無難なポップ・ミュージックが増えたような気がします(笑)。
その後、ワールド・ミュージックと呼ばれる音楽が幅広く聴かれるようになると、そういう要素もジャズに入ってきました。ジョン・マクラフリンは70年代の半ば、すでにインド人のメンバーと一緒にシャクティというグループでレコードを作っていました。またラテン音楽も、ジャズに盛り込まれたのはもっと昔の話で、40年代のディジー・ギレスピーあたりまで遡ります。思えば、ジャズとは常にそういう音楽だったのかもしれません。
一方で、80年代初頭にはウィントン・マルサリスを筆頭に、かつてのモダン・ジャズをもう一度再現する新伝承派と呼ばれる人たちが台頭してきましたが、僕は個人的にそういう音楽には面白さを感じることができませんでした。むしろ、ウィントンのお兄さんのブランフォード・マルサリスがバックショット・ルフォンクというユニットでやっていたような、ソウルやヒップホップの要素を採り入れた同時代性の強い音楽にこそ、ワクワクするものを感じていました。


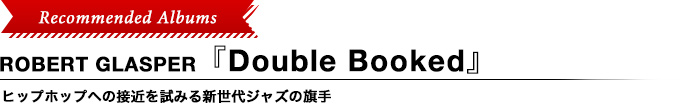
ロバート・グラスパーは、アクースティックに聴かせる“トリオ”、そしてヒップホップ的なアプローチの“エクスペリメント”という2つの異なる編成を従えていますが、今回はエクスペリメントとしての来日公演でした。僕は過去に両方のライヴを観ていますが、今回も素晴らしいステージでした。ビートはヒップホップ時代のファンクなんだけど、ストレートなファンクではなく、かなりシンコペーションを効かせたもので、それがニュアンス的にジャズだと思わせるんです。少なくとも、ジャズと聞いてみんなが連想するようなビートではない。そんなビートを受けて、グラスパーのピアノはそこまでファンクに寄っていなくて、わりとジャズっぽい。デリック・ホッジのエレクトリック・ベースはファンクとジャズ両方の要素を感じさせていました。ルックスも奇抜で、いちばんファンクの部分を出していたのはサックスとヴォコーダーのケイシー・ベンジャミンでしょう。そして、途中からモス・デフ(現ヤシーン・ベイ)との共演が始まると会場もいっそう盛り上がっていました。面白かったのはラッパーであるモス・デフが歌もけっこう披露していたことで、これがなかなか上手い。すごくいい組み合わせだったと思います。
さて、ロバート・グラスパーは“エクスペリメント”として発表した『ブラック・レイディオ』(2012年)に続き、さらに今年10月には『ブラック・レイディオ2』も発売されます。そんな彼をこれから聴いてみようという読者にお勧めしたいのが、“トリオ”と“エクスペリメント”両方の演奏を収録した『ダブル・ブックド』(2009年)です。これを聴けば、ヒップホップがちょっと苦手なジャズ・ファンも振り向かせることができる画期的な存在だということがわかると思います。見た目はけっこうごつい身体にユルユルのTシャツ。こんな恰好で一体どんなジャズをやるんだろうと思われるでしょうが(笑)、アルバムの前半を聴けばわかるとおり、演奏テクニックはかなりのものを持っています。
考えてみれば、現在35歳のロバート・グラスパーもヒップホップ世代の1人です。当時のヒューストンのラジオで何を耳にしたかといえば、たぶんそればかりでしょう。もちろんジャズが好きで勉強していたのでしょうが、それ以外の音楽も当然、彼の体内に早くから入っているはずですから、それが出ないほうがおかしいのかもしれません。今後は、彼の世代の他のジャズ・ミュージシャンからも、益々新しい音楽が生まれてくるんでしょうね。
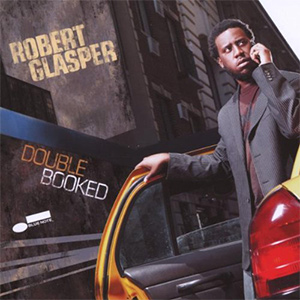





自分の音楽のバックボーンはアフリカだとはっきり言っているのがオマール・ソーサですが、彼のライヴではさらにいろいろな要素が聴き取れます。1曲の演奏がけっこう長いんですが、出だしのところで「ああ、こういう雰囲気か」と思うと、急に方向転換して全然違うところに行ってしまう。ステージではいつもヴゥードゥーの祭司みたいな真っ白の衣装を着ますが、演奏を聴いていると、明らかに何かが「降りてくる」感じです(笑)。そこでインスピレーションを得ているのか、突然ガラリと変わるんですよ。内省的なピアノ・ソロを弾いたかと思えば、突如サルサのクラーヴェのリズムでノリノリになったり、はたまたアフリカっぽくなったり……。どう展開するのかわからないこのスリル(笑)。いい意味で予想を裏切ってくれるミュージシャンですね。
レコードはレコードで、全体を真面目に設計して作られていて、1つの作品としてちゃんと聴けるものになっています。オマールのアルバムは『ムラートス』(2004年)や『アフリーカーノス』(2008年)などもいいのですが、ここでは最新作の『エグン』(2012年)を推薦盤としましょう。このアルバムにはジャズを中心に、彼が持つクラシックっぽい部分やキューバ、アフリカ的な部分も反映されていることがわかると思います。
ちなみにこのアルバムは、マイルズ・デイヴィスの『カインド・オヴ・ブルー』に対するオマールの解答とも言うべき作品で、同アルバムの50周年記念としてバルセロナの国際ジャズ・フェスティヴァルから依頼された演奏が元になっています。聞くところによると、『カインド・オヴ・ブルー』のいろんなソロの細かい断片を組み合わせて、半年くらいかけて録音していったそうです。
マイルズはかつて50年代の頃、ニューヨークで観たアフリカのバレエの音楽に魅了され、それが『カインド・オヴ・ブルー』を作るきっかけになったと言われています。この作品の発想のおおもとにアフリカがあったことはオマールももちろん知っています。そこで『カインド・オヴ・ブルー』の音をかなり詳細に分析して、細かい部分をつまんで再構築し、もう一度自分のフィルターにかけてアフリカに戻したのがこのアルバムだと僕は理解しています。皆さんにはどう聴こえるでしょうか。

今回のお勧めライヴは、11月26日(火)〜28日(木)に東京・丸の内コットンクラブで来日公演を行うセシル・マクロリン・サルヴァントです。彼女は2010年にセローニアス・マンク・インタナショナル・ジャズ・コンペティションのヴォーカル部門で優勝した新鋭のジャズ・ヴォーカリストです。見た目はちょっと年齢不詳だけど、まだ23歳なんだそうです。
今年7月に発売されたセカンド・アルバム『ウマンチャイルド』を手に取れば、1曲目の「セント・ルイス・ギャル」を聴き終わらないうちに、いかに彼女が大物かがわかります。特にすごいテクニックをひけらかしているわけではないんだけど、「恐れ入りました」って感じです(笑)。カリスマ性も感じるし、こういうヴォーカリストは実際にお客さんを前にすると、もっとすごい歌を聴かせてくれるのではないかな。
5曲目「あなたの膝に額をのせて」はフランス語で歌っているのですが、これだけジャズ・ヴォーカルとしての表現力を身につけていながら、英語以外の言語でもしっかり歌えることに、ちょっと驚きました。11曲目の「月光のいたずら」は誰でも知ってるスタンダードですが、こういう歌い方は聴いたことがありません。この人の声は、すごく昔の歌手のようにも聴こえるし、同時にものすごくモダンでもある。この若さでジャズ・ヴォーカルのアプローチを全部知っているんじゃないかと末恐ろしくなります。これが30歳代になったらどうなるんだろう(笑)。
僕はいわゆる典型的なジャズ・ヴォーカルをあまり聴きません。カサンドラ・ウィルソンやディー・ディー・ブリッジウォーター、アビー・リンカン、ベティ・カーターなど何人かを別にして、それほど積極的に聴くほうではないんです。セシルは人から薦められたので、それじゃあ一応と思って聴いたら「おお!」って(笑)。アルバム全体でいろんなタイプの歌をこなしていて、上手いんだけど自然体でもあるような……。オマール・ソーサと同じで、いい意味で予想を裏切ってくれるところが面白い。早く生の声を聴いてみたいですね。

今回のA Taste of Musicでは、ジャズを巡る新しい動きについてお話ししました。ジャズに限らず、音楽は変わり続けないと面白くない。進化が止まれば音楽シーンも淀んでしまう。思えば、単純な話なんです。もちろんレコードというものは、時間の流れの中の一瞬というか、ある時点のスナップ・ショットみたいなもので、気に入った人は繰り返し聴くわけですね。そして、生の音楽のほうは聴く度に映るものが変わるスナップ・ショットと言えるかもしれません。そこには進化し続ける今の音楽の姿を垣間見ることができるわけで、それがライヴというものの醍醐味でしょう。

試聴したリスニング・システム:ORACLE CD2000 mk2(CDプレーヤー) with ACOUSTIC REVIVE DSIX-1.0PA[BNC] , RBR-1、DCS Delius DSD(D/Aコンバーター) with ACOUSTIC REVIVE XLR1.0PA Ⅱ、LUXMAN C-600f(コントロール・アンプ) with ACOUSTIC REVIVE XLR1.0PA Ⅱ、LUXMAN M-600A(パワー・アンプ) with ACOUSTIC REVIVE SPC-PA[DOUBLE]、BOWERS & WILKINS 802 series Diamond(スピーカー)

第2回“A Taste of Music”をサポートしてくれたのは、オーディオ・アクセサリー・ブランドのACOUSTIC REVIVE。各種ケーブルやオーディオ・ボード、ルーム・チューニング用製品など多彩なライン・アップが揃っています。


























































